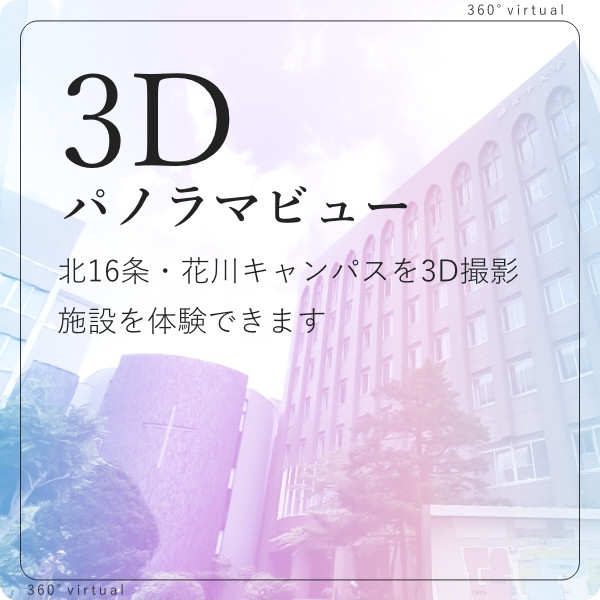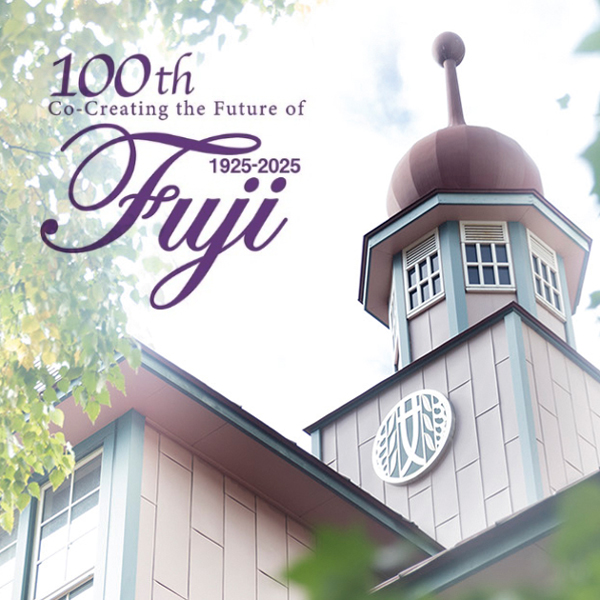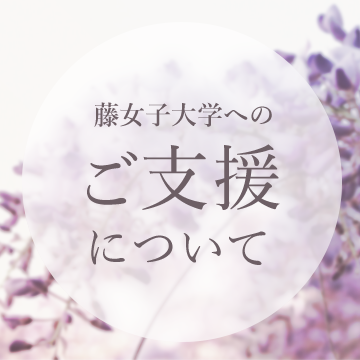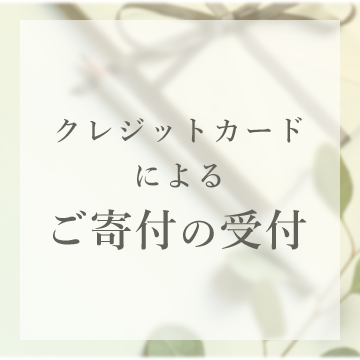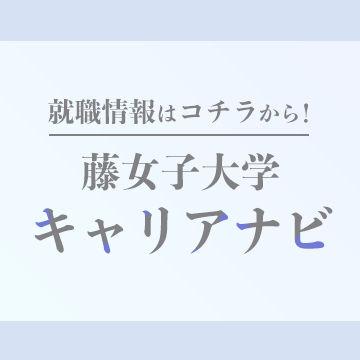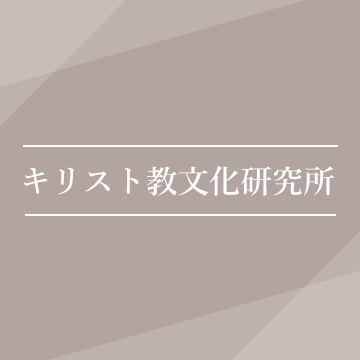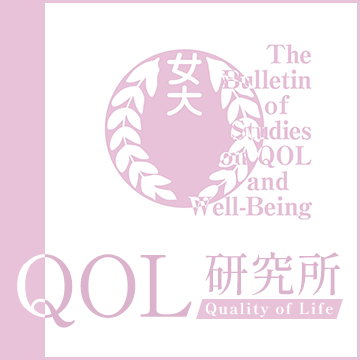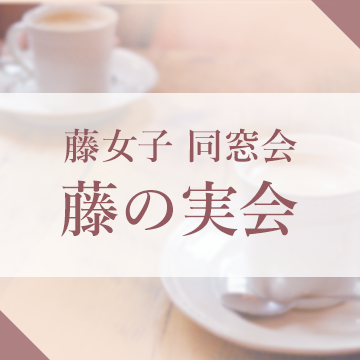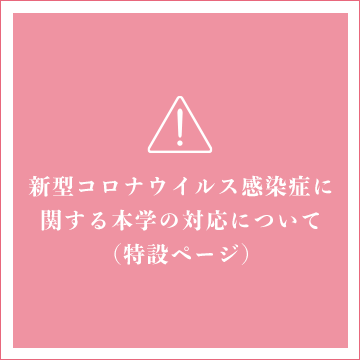Pick upピックアップ
広報活動
view more
すべて
- すべて
- プレスリリース
- 広告関連
- メディア関連
-
2024.04.25メディア関連本学食物栄養学科の学生の取り組みが北海道新聞(石狩版)朝刊に掲載されました
-
2024.04.22メディア関連本学人間生活学科の長尾順子准教授のコメントが北海道新聞朝刊に掲載されました
-
2024.04.01プレスリリース新学長就任と2025年度学部?学科名称変更について
-
2024.04.01プレスリリース【法人公告】学校法人藤天使学園について
-
2024.03.26メディア関連本学人間生活学科の大友教授が取材を受けた記事が「ケアスル介護」に掲載されました
-
2024.03.12メディア関連本学人間生活学科の木脇奈智子教授のコメントが北海道新聞朝刊に掲載されました
学部?大学院等確かな人間力と社会に役立つ知識を
研究?社会連携
社会に貢献し 地域とつながる
地域や企業、行政等との連携や、学外における様々な学びの機会を通じて、学生と社会のつながりを大切にしています。






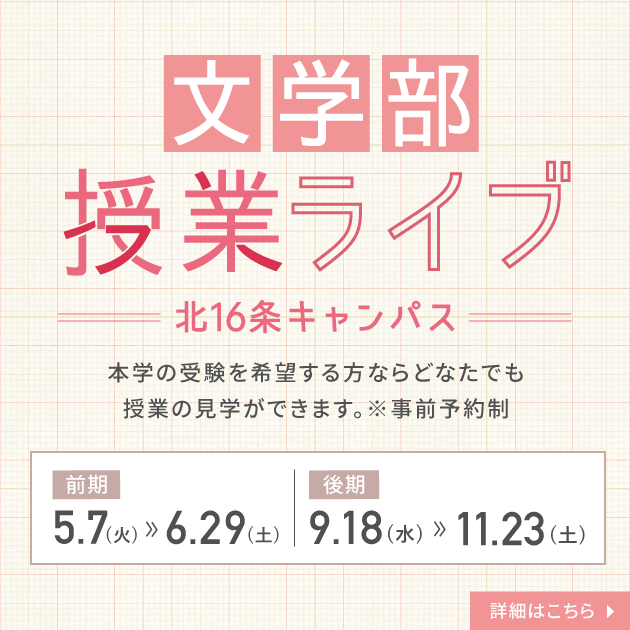


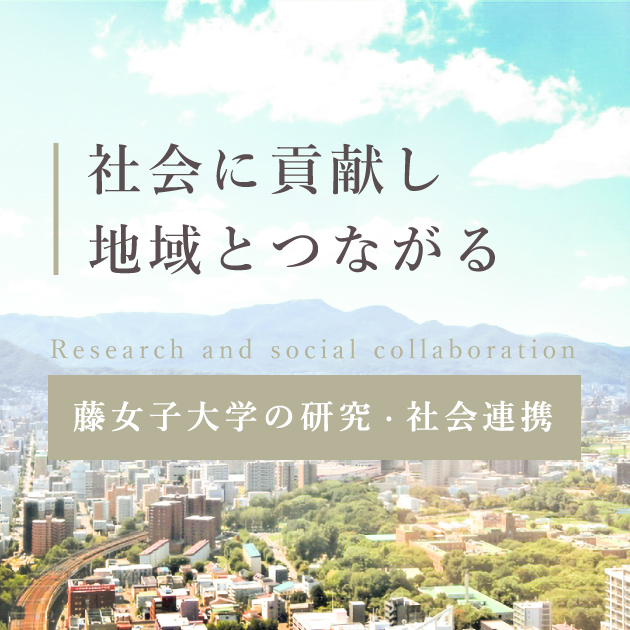

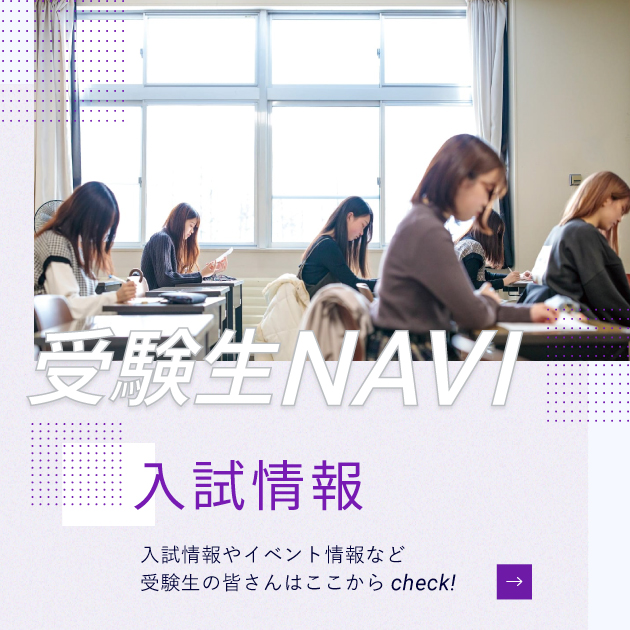
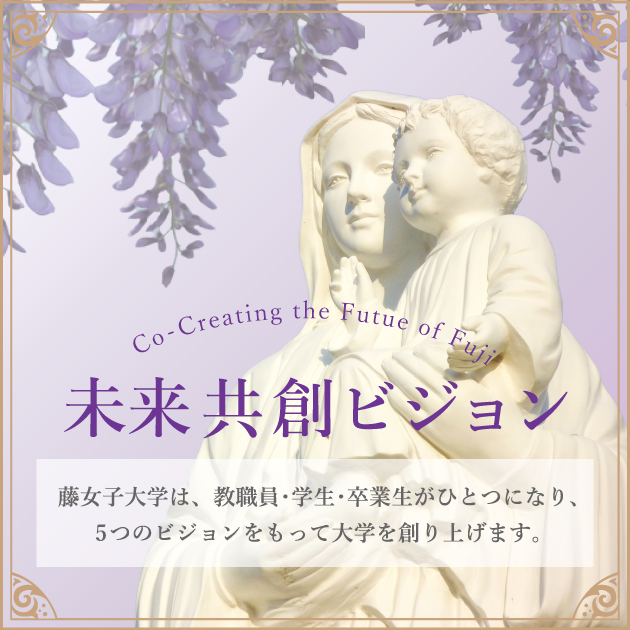








.jpg)



.jpg)